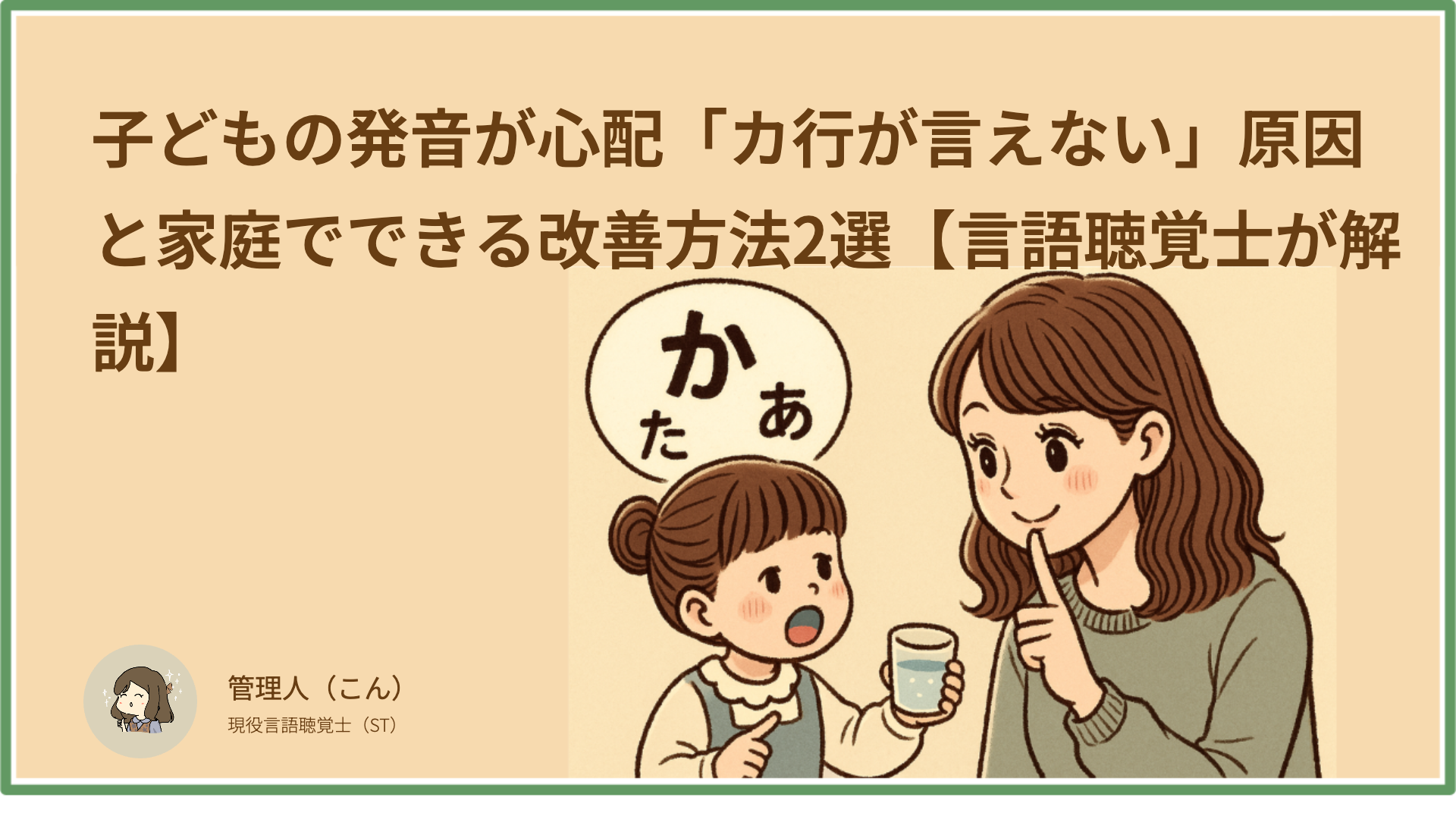お子さんの発音が心配なご両親へ【言語聴覚士が解説します!】

〜 家庭での関わりと専門家への相談時期について〜
「うちの子、ちゃんと話せていないなあ〜」と、子どもの発音について心配していませんか。上手に発音できていない場合、親としてどうしてあげらたいいか心配が募りますよね。
実は、発音の問題は成長とともに自然に改善する場合が多いです。また一方で、一定の時期を過ぎても改善しない場合もあり、その場合は適切な時期に適切な訓練を受けることで、毎日の生活を安心して楽しく過ごせるようになります。
この記事では、発音の悩みを解消するためのポイントや、発音訓練が必要かどうかを判断する方法を分かりやすく解説します。
子どもの発音が心配なとき、まず確認すべきこと

うちの子は、もうすぐ5歳なのに、「かきくけこ」や「さしすせそ」がうまく言えていないわ。どうしたらいいの?

それは心配ですね。これから、今できる対応と、今後の見通しについて解説しますね。ぜひ参考にしてください。
正しい発音の発達時期とは?
子どもの発音は成長とともに発達していきますが、年齢に応じた目安を知ることで、適切な対応ができるようになります。小児専門の言語聴覚士の視点から、発音の発達目安を詳しく解説します。
1. 乳児期(0–1歳):音を聞いて声を出す準備期間
乳児期は、発音そのものよりも音を聞き、声を出す準備を整える時期です。特に発音などを気にする必要はありません。
2. 幼児期前半(1–2歳):単語の発音が始まる時期
1歳を過ぎると、子どもは単語を少しずつ発音し始めます。最初ははっきりしない発音でも、成長とともに明瞭になっていきます。まだ多くの音は不明瞭で、聞き慣れた人が理解できる程度です。この時期のお子さんは、繰り返し聞いて真似することで、発音を学びます。ご両親が少しゆっくめに正しい発音で話しかけてあげてください。
3. 幼児期後半(3–5歳):発音の基礎が整う時期
3歳頃になると、多くの音を正確に発音できるようになりますが、難しい音はまだ習得途中です。
- 3歳:母音(あいうえお)と簡単な子音(た行、な行など)はほぼ正確に発音できます。サ行やラ行、カ行はまだ不明瞭なことが多いです。
- 4歳:サ行やカ行が徐々に明瞭になり始めます。発音できる音も多くなり、周囲の人にも理解されやすくなります。
- 5歳:ほとんどの音を正確に発音できるようになりますが、個人差があります。
発音が悪い原因とは?
正しく発音するために必要な口腔機能について、説明します。
1.発音するための口、舌、鼻の機能は?
口や舌の機能としては、反対咬合、舌小帯短縮症、口唇口蓋裂、鼻咽腔閉鎖不全などがあり、これらは正しく発音するための困難さを引き起こします。これらは、歯科検診や1歳半健診などでもチェックが入りますので、心配な場合は相談しましょう。鼻咽腔閉鎖不全があると、声が鼻から漏れ聞きづらい発音になります。赤ちゃんのときにミルクが鼻から漏れることがあったり、「ふがふが」としゃべっている場合は要注意なので、保健センターの保健師さんに相談してみましょう。
2. 口腔機能の未熟さ
「カ行」は、舌の奥の方を上顎につけて弾かせるとできる音、「サ行」は舌と上顎で息の摩擦を作って発音するなど、細かい緻密な動きを必要とします。日本語の発音は、特に「カ行」「サ行」「ラ行」において、かなり難しい口の中の筋肉の動きが求められます。これがお子さんの「カ行」や「サ行」「ラ行」を言えない原因に繋がっています。
発音の問題にどう対応する?日常生活でできる工夫
親子で楽しめる発音練習ゲーム
簡単に取り組める発音練習法を簡単に紹介します。
1.2歳から4歳ぐらいまでにおすすめの発音遊び
・口や舌をたくさん動かす遊びをしよう。
固いものを食べる。舌でペロペロ舐める。吹く遊びをする。
・身体をたくさん動かして遊ぼう!
・指先を使う遊びをしよう!
※詳細は下記をご覧ください。

2.4歳から5歳におすすめの発音遊び
・◯のつくことばあそび
・しりとり
・文字学習
・絵本を一緒に読もう
※詳細は下記をご覧ください。


正しい発音を促すコミュニケーションの工夫
お子さんの発音が悪いと、ママパパはお子さんを育てる責任感から、どうしても発音を訂正したり、もう一回ゆっくりはっきり言ってごらん、などと対応してしまいます。でも、それはNG対応です。
お子さんも精一杯自分の持てる力を発揮しておしゃべりしているのです。発音が治ってほしい、上手にお話してほしいというママパパのお気持ちは察しますが、以下の対応をしていきましょう。
1.言い直しをさせない
2.ゆっくり区切って伝える、言わせることはNG
3.発音の良し悪しではなく、お話の内容を聴こう
4.親が発音の訓練をするのはやめましょう
お気づきだと思いますが、これらの対応で発音が治るわけではありません。でも、ママパパがお子さんの話をたくさん受け止めてくれて、いっぱいお話したい!という思いがあると、口の周りの動きが促されて、自然と改善方向に向かう可能性があります。お子さんが発音に対するプレッシャーを感じず、たくさんおしゃべりしてくれる環境を目指しましょう。
発音の訓練は、適切な時期に適切な内容で行うことで、発音の改善はかなりの高確率で見込めます。なので、心配しすぎず見守ることが必要な時期があります。
発音の訓練や専門家への相談が必要なサイン
どんな場合に相談すべき?
日々の対応に気をつけたり、口の運動を促す遊びにも取り組んでみたけれど、なかなか改善しないな、このまま様子をみていてもいいかな、など不安な場合の対応を、年齢と具体的な状態に分けて解説します。
1.1歳〜4歳の場合
・おしゃべりしているときに鼻から声が漏れるような「ふがふが」している感じがなければ、特に相談する必要なありません。上記の遊びと対応を続けていきましょう。
・鼻から声が漏れるような「ふがふが」している場合や声の出し方、発声の仕方がちょっと違う場合には、3歳児健診で保健師さんに相談してみましょう。耳鼻科の医師に相談してみるのもいいと思います。
2.5歳以上場合
・特定の発音が言えたり言えなかったりする場合
この場合は、いずれ言えるようになる可能性が高いので、すぐに相談する必要はありません。もう少し様子をみてもいいでしょう。お子さん自身がうまく言えないことに気づき、おしゃべりすることを躊躇している場合は、保健センターの保健師さんに相談してみましょう。
・特定の発音が全く言えない場合
地域の担当の保健師さんに相談してみましょう。それぞれの地域で発音の指導へのつなげ方は様々です。一番詳しいのは、保健センターの保健師さんなので、躊躇せずに相談してみましょう。保健センターの言語聴覚士に繋いでくれたり、言語聴覚士がいる病院を紹介してくれたりするはずです。
お子さん自身がうまくお話できないことや発音が悪いことに気づいている場合には、5歳のお誕生日前であっても相談を始めることをお勧めします。
言語聴覚士に相談するメリットとは?
では、保健師さん等から言語聴覚士につながった後は、どんなことをするのでしょうか。言語聴覚士が行う専門的な評価や訓練の流れを紹介します。
1.発音の状態をアセスメント(評価)します。
・「構音検査」と言って、発音をみることに特化した検査を行います。絵カードを見せてカードに書かれた絵の名前をお子さんに言ってもらう検査です。もう一つは、言語聴覚士が言ったことばや文章を真似してもらいます。お子さんの発音の誤りに一貫性があるのか、ないのか、真似するときは上手に言えるのか、環境要因があるのか、などいくつかの側面で発音を評価します。また、必要な場合は、発音以外の言語発達面全般の評価も行います。
・ママパパから、日常場面での様子を伺います。これまでの発音の様子について、現在の家庭でのおしゃべりの様子、保育園幼稚園でのおしゃべりの様子、お子さん自身が発音を気にしているのかどうか、などを聞き取りさせていただきます。
2.発音訓練の必要性、適応時期を保護者の方と相談します。
・特定の音を必ず誤る場合、例えば「せんせい」が「てんてい」となる、「かまきり」が「たまちり」の場合は、なるべく幼児期に発音の指導を受けることをお勧めします。特にお子さん自身に発音の誤りヘの気づきがある場合は訓練指導を受けましょう。
・特定の音が発音できたりできなかったりする場合は、もう少し様子を見る場合もあります。3ヶ月後、半年後にもう一度発音の様子を評価させていただき、訓練の適応を判断します。
3.発音訓練の実際
・発音訓練の頻度は、基本的には週1回程度、1回40分程度で行います。保育園幼稚園の後、ママパパと一緒に療育センターや病院に通い、言語聴覚士とお子さんで行いますが、ママパパも隣で見ていただきます。
・発音訓練の内容ですが、発音しにくい音、例えば「サ」や「カ」などを発音するための舌の使い方などを練習していきます。言語聴覚士と一緒に行った発音練習を定着させるために、宿題を出すこともあります。大変ですが、頑張って取り組んでください。毎日10分あればこなせる内容です。
練習方法はかなりしっかりと確立していますので、言語聴覚士であれば対応することができます。
・訓練の期間は、お子さんそれぞれの状態によって違ってきます。また、練習する発音がいくつあるのかも訓練期間の長短に影響します。アセスメント後の訓練開始時に、おおよその見通しを言語聴覚士に聞いてみてください。

心配が続くようであれば、ぜひ言語聴覚士に会いにきてくださいね。